Poetry Live Scroll 01 「詩情」の変換:AI時代に編む言葉
オンライン・トーク・イベント
Poetry Live Scroll 01
「詩情」の変換:AI時代に編む言葉
日時:2024年5月25日(土)20:00-22:00
開催方法:オンラインイベント(YouTube配信)
*この配信はリアルタイム視聴と1ヶ月後までのアーカイブ視聴でお楽しみいただけます。
出演者:円城塔、布施琳太郎、平川綾真智(司会)
料金:一般=¥2,000、学生=¥1,500
申し込み(Peatix):
https://poetrylivescroll01.peatix.com/
.jpg)
【イベント概要】
AIを起点として、芸術の最先端を徹底的に深めるトーク・イベントです。
最先端のトークを聞きながら、主催団体メンバーや視聴者がYouTubeのコメント欄で意見を交わし楽しみ、皆で学び合うイベントです。質疑応答の時間もあります。
皆の生活で存在感を増すAIの立ち位置、そして芸術の未来、言葉の未来。どれか一つにでも興味ある方は、是非ご参加ください。
主催:poetry interface
後援:思潮社
**********
【出演者より】
■円城塔さん
言葉が画像に、母語が非母語に「機械的に」変換されるのは非常に驚くべきことです。機械が言語的に動くものである以上、そこにはプレ言語的な言語という語義矛盾するものがうごめいているはずで、同時に巨大な詐術も埋まっているはずだからです。
■布施琳太郎さん
僕は自分のことを「相手にあわせて話し方を変える」タイプだと感じています。たぶん、自分が「自分であること」から離れたいから。今回も相手にあわせて変わりたいと思っています。そのために円城塔作品を読み込みつつ、人工知能とは何か、意味の空間AがBへ、そしてBからCへと生成するシステムが何を意味するのかを考えたい。語と語をつないで文をつくるための素子が、be動詞から前置詞になったような世界で、いまだ詩を書くことはできるのか。思考することはできるのか。最高速度で駆け抜けたいです。
■平川綾真智さん
生成AIは無数の可能性の中から、複雑性を縮減する行為を通じて、機能的なシンボルを私たちに発信しています。深層心理を可視化していくかのようなこの技術は、それ自体が詩的な産物とも言えるでしょう。芸術的側面から、技術が解きほぐされる瞬間に是非ご期待ください。
**********
出演者紹介

■円城塔
1972年生まれ。作家。2007年「オブ・ザ・ベースボール」で文學界新人賞受賞。 著作に『烏有此譚』(野間文芸新人賞)、『道化師の蝶』(芥川賞)、『屍者の帝国』(伊藤計劃との共著、日本SF大賞特別賞)、『文字渦』(表題作に川端康成文学賞)など多数。(写真:新潮社)

■布施琳太郎
1994年生まれ。アーティスト。スマートフォンの発売以降の都市における「新しい孤独」や「二人であること」を多様な手法で実践。23年に詩集『涙のカタログ』、評論集『ラブレターの書き方』を上梓。24年、「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」(国立西洋美術館)に参加。(写真:岡崎果歩)
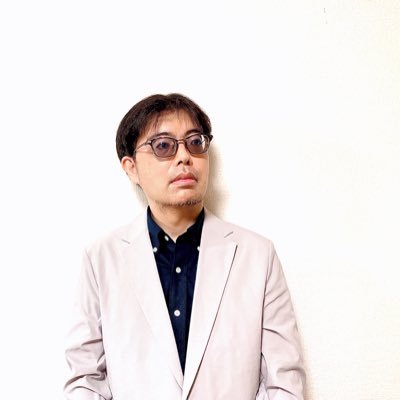
■平川綾真智
1979年生まれ。詩人。詩誌での活動と並行し、2000年以降のweb上の詩の潮流をリード。「シュルレアリスムと音楽」の数少ない研究者の一人。詩集に『h-moll』(2021/思潮社)など。個展に、NFT現代詩展『転調するために』(2023/メタバース美術館)。「poetry interfere」創立メンバー。
**********
poetry interface
――言葉に出会い直す、未来と接続する――
「poetry interface」は、日本語の詩情に再び出会うために動き出したプロジェクトです。
HP
https://poetryinterface.com/
X(旧Twitter)
@poetryinterface
@poetryinterface